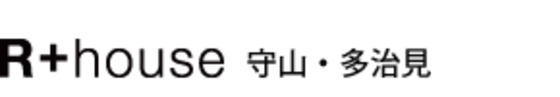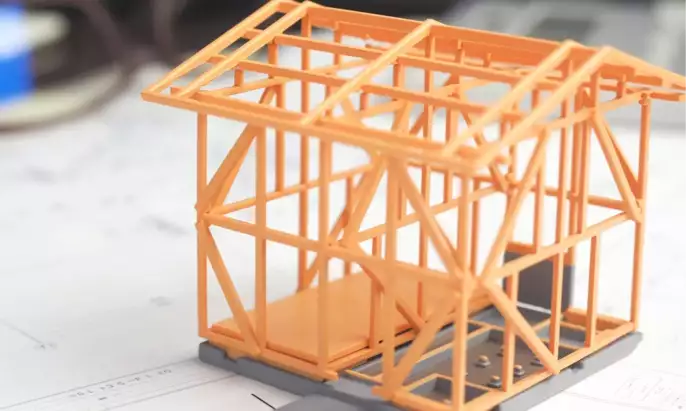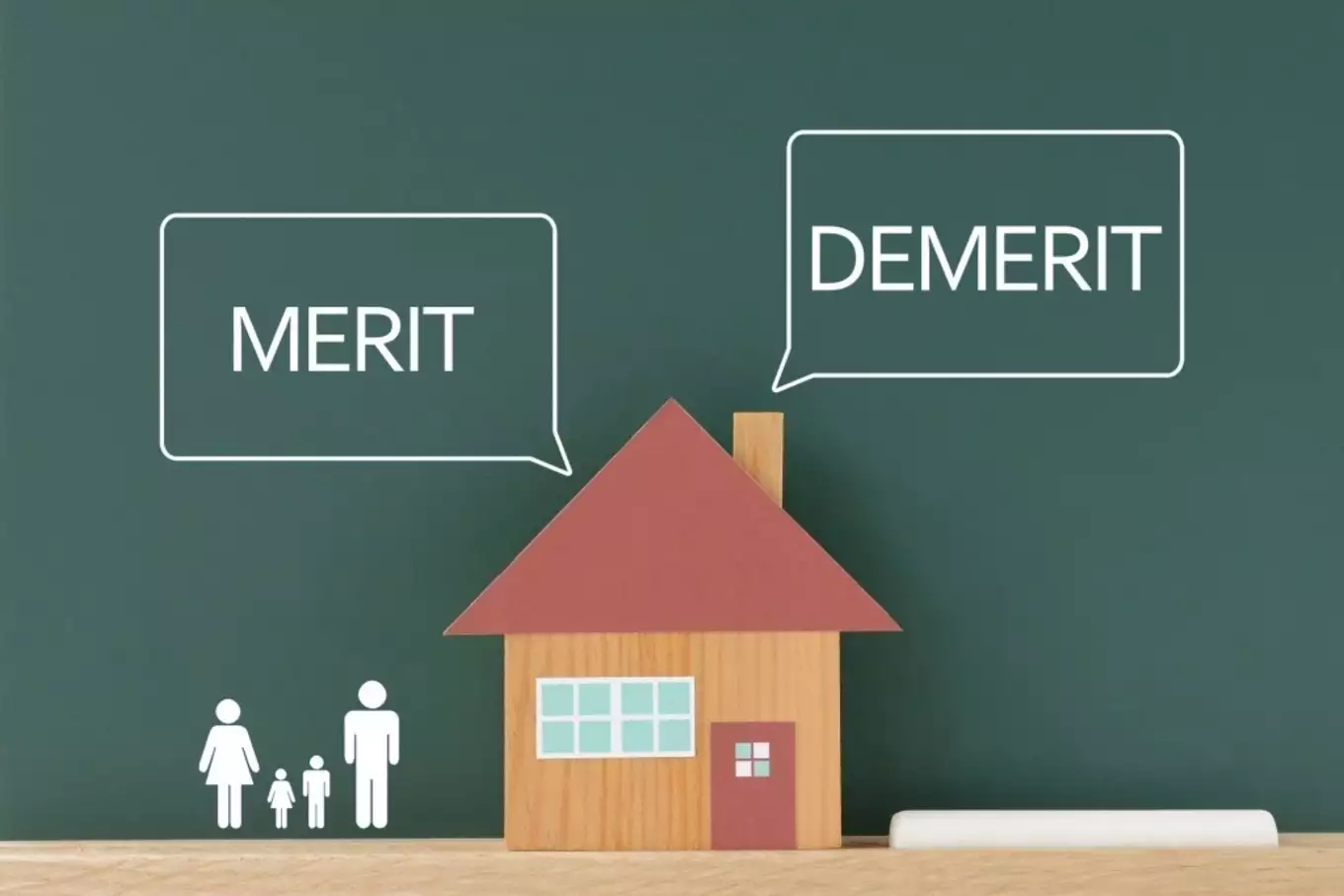断熱等性能等級とUA値について

断熱等性能等級とは
断熱等性能等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められている省エネ性能を表す等級を示したものです。これまでに何度も見直されてきており、直近では2022年4月に等級5、2022年10月に等級6、7が新たに設置されました。等級ごとの断熱性能のレベルを以下の表にまとめました。
等級ごとの性能レベル
等級3:
1992年制定。一定レベルの省エネ性能を満たしている。
等級4:
1999年制定。
壁や天井、窓、玄関ドアなどの断熱性が必要なレベル。
等級5:
2022年施行。窓ガラスや断熱材などは、等級4よりも高いレベルの断熱が必要。
等級6:
2022年10月施行。
冷暖房にかかる一次エネルギーの消費量を約30%削減できるレベルの断熱性能。
等級7:
2022年10月施行。
冷暖房にかかる一次エネルギーの消費量を約40%削減できるレベルの断熱性能。
1992年制定。一定レベルの省エネ性能を満たしている。
等級4:
1999年制定。
壁や天井、窓、玄関ドアなどの断熱性が必要なレベル。
等級5:
2022年施行。窓ガラスや断熱材などは、等級4よりも高いレベルの断熱が必要。
等級6:
2022年10月施行。
冷暖房にかかる一次エネルギーの消費量を約30%削減できるレベルの断熱性能。
等級7:
2022年10月施行。
冷暖房にかかる一次エネルギーの消費量を約40%削減できるレベルの断熱性能。
UA値とは
断熱等性能等級を判定するために使用するのが、UA値(外皮平均熱貫流率)です。以降で説明する「省エネ基準」や「ZEH基準」などにも設定されています。断熱性能を判断する指標となるUA値は、外皮(外壁や屋根、窓、ドアなどの開口部)を介して住宅内部の熱がどのくらい逃げるのかを示しています。そのため値が低いほど熱の移動が少なく、断熱性能が高いことを意味します。逆にUA値が大きいと、断熱性能が低いことになるのです。
また、断熱性能は気候に合わせたレベルを選ぶ必要があります。そのため日本では国内を8つの地域に区分し、その地域ごとに断熱性能の基準を定めています。
また、断熱性能は気候に合わせたレベルを選ぶ必要があります。そのため日本では国内を8つの地域に区分し、その地域ごとに断熱性能の基準を定めています。
住宅に必要な断熱性能のレベルは?

省エネ基準に適合した家づくりが義務化へ
「2050年カーボンニュートラルの実現」や「2030年度温室効果ガス46%排出削減」などの政策目標を背景として、省エネ基準の見直しが行われつつあります。そんな中、2022年6月に建築物省エネ法が改訂され、原則すべての建築物において省エネ基準を満たすことが義務付けられることになりました。
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法とは、2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の略です。これまでこの法律では、戸建て住宅における省エネ対策として、基準を満たす義務付けはされていませんでした。しかし、改定では建築主に対して建築物のエネルギー消費性能向上の努力義務、また建築士に対しては、建築主が省エネ性能向上に向けて努力できるよう説明する努力義務などが課せられることになりました。
さらに省エネ基準適合も拡大されることとなり、2025年4月には、すべての新築住宅において省エネ基準を満たすことも義務付けられます。
さらに省エネ基準適合も拡大されることとなり、2025年4月には、すべての新築住宅において省エネ基準を満たすことも義務付けられます。
省エネ基準とは
省エネ基準は、断熱等性能等級4に値する基準です。今後2025年4月以降はこの基準が最低水準になるため、今後注文住宅を予定しているのであれば、クリアしているほうが良いでしょう。ただし省エネ基準は、今の建築技術において高い断熱性能ではありません。すでに長期優良住宅の基準は断熱等性能等級が4から5に引き上げられていることからみても、今後等級5以上が標準となる可能性は高いと考えられるでしょう。
ZEH基準とは

HEAT20とは
HEAT20とは、「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」がエネルギーや地球温暖化問題の対策のために、2009年に発足した基準です。UA値だけでなく、省エネ基準の住宅と比較した暖房負荷削減率や、暖房使用時期の最低室温なども定めています。断熱性はG1~G3の3つに分類されています。
それぞれの基準のUA値
各基準のUA値を地域区分ごとにまとめると以下の表のとおりとなります。